前ページ/Page 7/次ページ

パネルディスカッション
「表現の自由と平和について」



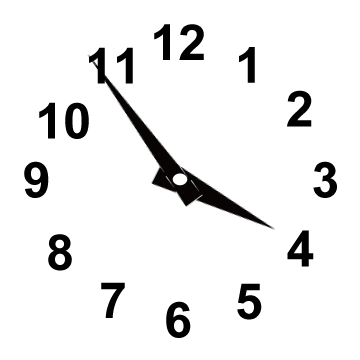 大熊/国会議員を目指していただけあって、すばらしいまとめ方でございましたけれども。それでは高鶴さん、最後にお願いいたします。
大熊/国会議員を目指していただけあって、すばらしいまとめ方でございましたけれども。それでは高鶴さん、最後にお願いいたします。
どうやったら、この表現の自由と平和を守って行けるか。私、一番大事なことは、気づくということだと思います。気づくこと。気づく能力。気づく感性を自分の中に育てていくことだと思います。何かが変えられようとしているとき、何かが付け加えられようとしているとき、何かが削られようとしているとき、それを受け入れるということは、そのあとにどのような事態が続いていくのか。そこを考えることのできる能力。これを自分の中に培(つちか)っていくこと、大事だと思うんです。
さっき、鶴彬のお話をさせていただきました。彼が拘束されて命を落とすことになった原因は、治安維持法という法律でした。ただ、この治安維持法、1925年(大正14年)にできたものなんですけれども、できた当初の姿であったなら、鶴彬が拘束されることはなく、命を落とすこともなかったんです。じゃあ、何でそんなことになったか。
この法律は、できてから3年後の1928年(昭和3年)に大きな改定が加えられます。最高刑が死刑になったり、予防拘禁の仕組みが整ったりという、そういう改定もあるんですけれども、ものすごく大きなことは、この法律が目的遂行罪化されたということでした。どういうことか申し上げます。
最初の1925年時点の治安維持法では、処罰される対象となっているものは、2種類でした。一つ、国家を転覆する可能性ある結社を組織した者。二つ、その結社がそういう性格を持っているものだと知りながら、そこに参加した者、入った者。この2つだけだったんです。
ところが3年後、もうひとつ加わります。「その結社の目的実現の為になる行動を取った者。」例えば、共産主義革命を起こそうとしている結社があったらば、その為になるような行動を取った者も処罰の対象となってしまった。
例えば、毎朝散歩をしている人がいるとしますよね。あるいは、畑で、一生懸命耕して、大根を作ってる人がいるとします。毎朝散歩をしている人に対しては、「けしからん。いずれ起こる革命に備えて、革命の戦士となるべく、体を鍛えているのだな。」畑で大根作ってる人に対しては、「そういう革命を起こす結社に対する支援物資を、おまえ作ってるんだな。」ということで、逮捕になるわけです。
逮捕される、拘束されるということは、私たちが持っている基本的人権に対する大きな疎外です。もし1928年の時点で、社会にいる大勢の、大半の人が、これは、ほんの二十数文字を法律の条文に書き加えただけの改定だったんですけども、その二十数文字を書き加えることが、やがてどんな社会に繋がっていくのかということを、気づいて、立ち止まって考える方が、社会の大半であったなら、そういう改定って、起こり得なかったんです。鶴彬だって、そんなことで拘束されて死ぬことはなかったんです。 だから、そういう社会を創っていくというのは、私たち一人ひとりの心の問題なんだと思うんですね。もうちょっと言えば、どうやったらそういう能力って養えるんだろうって話になるかと思います。
これについては、表現するという行為と向き合うということが、大きな力になると断言できます。ただ、表現って言うと、例えば音楽を奏でる、絵を描く、ものを書くといったすでに認知された表現芸術と呼ばれるものだけが、表現行為だというイメージがどうしてもありますよね。私、これ、もうちょっと広げて考えていいんじゃないかと思うんです。
私たちって、ある日突然、この世っていう世界に放り込まれた存在なんです。そういう存在である私たちに対して、世界はいろんなもん見せてくれるじゃないですか。例えば、真っ青な空。きらきらした雲。「ああ、いい風だなぁ」っていう涼風。波。音。森の茂り。いろんなもん見せてくれます。それっていうのは、世界が、私たちに与えてくれている宝物、贈り物なんです。
で、そういう働きかけに対して、私たちの心っていうのは、無反応でいられません。意識するとしないにかかわらず、反応を返しているんです。
窓を開けて、「きょうはいい日だなぁ」と言って、ほおっと漏らすため息もそうです。それこそ為政者の何かに対して、「けしからん」と思う。これも、そうした反応のひとつなんです。
表現する、とは、表(おもて)に現(あらわ)すと書きます。世界がそうやって送り届けてくれた贈り物に対して、私たちの心の中に何かが浮かぶ。それを外に表す。これが表現だ、というふうに私は考えています。
表現というのは、特定の創作の分野に携わる人たちだけに許されている、その人たちのみに関わる行為ではなくて、生きている人すべてに託されている行為だと思うのです。人だけじゃないですよ。伸びする猫だってそうです。ポカポカした中で。表現行為というのは、意識のある生命体すべてに委ねられている宝の鍵なんじゃないかっていう気がします。
但し、表現には深浅があります。
川柳は、「吐く(はく)」と言います。二日酔いなんかで、げぇーって吐く、のあの「吐く」です。
ここまでは昔から言い伝えられていることでした。そこで私は考えました。そうか、川柳を書くことを「吐く」って言うのか。吐くからには、何か(お腹を指して)ここにないと吐けないじゃないですか。ですから、世界がそうやって送り届けてくれたものに反応した心、それをまず一旦深く呑むんです。
呑み込みが浅いと、外に向けて表せるものも浅くなります。でも、深く呑めば呑むほど、吐き戻すのはとても苦しくなりますけれども、深いものが外に出てきます。
原発反対のデモ。これも立派な表現行為です。経産省前で、ずうっと念仏をあげているお坊さまがいらっしゃいますが、その読経だって、ひとつの表現行為です。そういうふうに、それぞれがいろんなふうに思ったことを、深く呑み込んだうえで吐き戻す――。そのための鍵は、きっと私たち一人ひとりに授けられているんだと思います。
かつての治安維持法に加えられた改変は、たったの二十数文字でした。そんなことをしようとする人たちがいたときに、もしそれに気づかずに私たちがいると、例えば、反戦を扱った、平和を扱った映画を観たあと、「やぁ、いい映画だったね」ってつぶやいたひと言が、「おまえは国家体制を転覆させてようとしている」みたいな感じで取られても仕方がないような世界が、創られてしまうのかも知れません。私は、そんなふうには、したくないと思います。
みなさん、どうか「これが私だ」って言える表現手段を、ひとつでいいですから、手のひらに載せてみてください。きっと、その表現手段を手のひらに載せられたあとのみなさんの人生は、豊かで、強いものとなるのではないかと思います。(会場から拍手)
では、改めまして、今回いろいろお話を聴かせてくださいました、木津陽介さん、伊藤千尋さん、高鶴礼子さん、本当にありがとうございました。(会場から拍手が続く)
「伝える・知る・つながる」ことしのテーマですが、本当に力いっぱい伝えていただき、私たちもそれを知ることができました。感謝したいと思います。今という時代、本当にどうなのかなぁっていうことを、突きつけられるようなお話でした。
この3人の書かれたご本・作品が、このあとホワイエで販売されますので、ぜひお手に取っていただきたいと思います。高鶴礼子さんの本、伊藤千尋さんの本、それから、司会の大熊啓さんが編集に携わった『へいわのうたソングブック』。それぞれ販売されます。サインもしていただけますので是非お買い求めください。
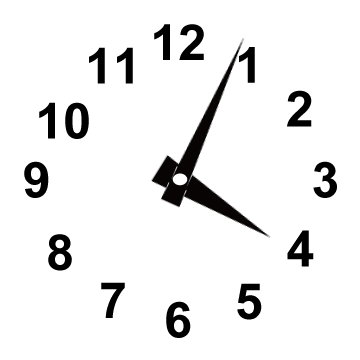
おわり