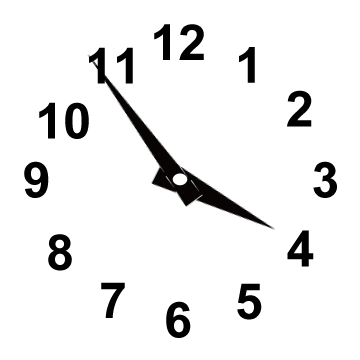パネルディスカッション
「表現の自由と平和について」



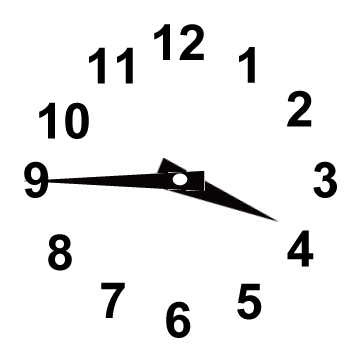 大熊/いろんなお話聴かせていただきましたけど、先ほどの鶴彬さんの話を含めて、伊藤さんのチェコの話もそうですが、表現しなければ、表現することを止めることはできない。たとえ、どんなに自由が奪われても、何らかのかたちで。「私を信じちゃいけないよ」というのも、うまく裏に入れてみたり、したたかに抵抗する人たちもたくさんいたというふうなお話を聴きましたけど、ちょっともお時間が迫っているわけですが、表現の自由というのは平和のひとつの保障といいますか、表現の自由があってこそ、先ほどの伊藤さんのお話、口を満たして、口から何でも言えるというお話がありましたが、今、世界や日本を見渡して、これから平和を守っていくために、また表現の自由というものを、しっかりと自分たちのものにしていくために、どういうことができるだろうか。また、改めてそれぞれの関わっている分野の魅力、そして鶴彬が呼びかけたような、「川柳人はこうあるべきだ」みたいなことを、それぞれの分野の方々への呼びかけや、きょう参加しているみなさんへのことばがありましたら、聴いていきたいなぁと思いますが、まず伊藤さんから。
大熊/いろんなお話聴かせていただきましたけど、先ほどの鶴彬さんの話を含めて、伊藤さんのチェコの話もそうですが、表現しなければ、表現することを止めることはできない。たとえ、どんなに自由が奪われても、何らかのかたちで。「私を信じちゃいけないよ」というのも、うまく裏に入れてみたり、したたかに抵抗する人たちもたくさんいたというふうなお話を聴きましたけど、ちょっともお時間が迫っているわけですが、表現の自由というのは平和のひとつの保障といいますか、表現の自由があってこそ、先ほどの伊藤さんのお話、口を満たして、口から何でも言えるというお話がありましたが、今、世界や日本を見渡して、これから平和を守っていくために、また表現の自由というものを、しっかりと自分たちのものにしていくために、どういうことができるだろうか。また、改めてそれぞれの関わっている分野の魅力、そして鶴彬が呼びかけたような、「川柳人はこうあるべきだ」みたいなことを、それぞれの分野の方々への呼びかけや、きょう参加しているみなさんへのことばがありましたら、聴いていきたいなぁと思いますが、まず伊藤さんから。
ドイツ女子団 (Bund Deutscher Mädel) を指す。1930年から1945年まで存在した、ナチス・ドイツがドイツに住む未成年の少女を統制するために設立した国家組織。訳語は一定しておらず、ドイツ少女同盟、ドイツ女子同盟、ドイツ少女団とも称される。 (出典:Wikipedia)
中南米にコスタリカという国がありますけど、この国は日本と同じく平和憲法を持ってます。この国の、僕が一番感心したのは、小学校の入学のときに、先生が最初に教えるのが、「だれもが愛される権利を持っている」ということばです。そして、もし愛されてないと思ったら、違憲訴訟に訴えることができる。ということを6歳で習うんですよ。
例えば、モーツァルト。今からどれぐらい前ですか?200年以上前ですよね。でも、いまだにやられている。バッハもそうです。なぜやられているのか。もちろん、分かりやすさ、聴きやすさもありますが、それだけではどうしても片付けられない部分があります。そこに、クラシックと呼ばれる古典。ずうっと大きな大河の流れです。根底に流れるものが変わらなければ、それが古典と呼ぶにしかるべきだと思います。そういった中で、新たな表現を取り入れていく、考え方を混ぜていくということが、再現芸術の使命なのかなと思います。
日本でもJ-ポップ、非常に発展してきていますが、1970年代-80年代と2000年代に入ってからとで大きく違うところは、まず、楽曲の速さ、テンポ感。それから、ひとつの音符でさばくことばの数。これが、70年代-80年代と2000年以降では、かなり違っています。それだけ社会がスピードアップしている。
あとは、自分自身の言いたいことを、より表現できるような環境にあるのかなというように、今思っているのですが、嘘のような本当の話なんですが、今の日本で、国会議事堂の前だったり、例えば、大使館があるような有栖川宮記念公園、麻布のあたりで「九条」のTシャツを着ていたりすると、職務質問に遭うとか、「平和」と書いてある封筒を持っているだけで、職務質問に遭うとか、という時代が今まさに日本で起きています。これは、なかなかメディアが報じません。
ということは、逆に今の世の中、私たち自身何をすべきかと言うと、自分で情報を取捨選択する。情報はあふれています。この取捨選択というのは非常に大事で、東大に入るためには何が必要ですか?勉強ではなく、取捨選択能力です。目の前にある情報から、何が必要で何が必要でないか。これを瞬時に見極めるという取捨選択能力。メディアが一方的に流している情報は、嘘であると疑ってかかることの大切さ。
こういったことが、これからの日本の中に表現をしていくという点では、まずやっていかなければいけないことなのではないかなと思います。それは、楽譜もしかりで、楽譜に書かれてあることが正しいというふうに教わるときもありますが、それも間違いです。楽譜どおりにやればいいのか。なんにも伝わりません。大事なのは、そこに演奏する人の感情、温度、思いがあるかどうかだと思います。
これだけデジタルテクノロジーが発達しているのにもかかわらず、人々はどうして歌い、ライブ、コンサートに足を運ぶのか。CDやデジタルからは、量り取ることのできない温度と空気。それを体感することが、音楽というものの表現を完成させているからだと、私は思っています。ですので、これからもそういった温度や空気を、みなさまに伝えられるようなかたちで、活動をしていきたいというふうに考えております。(会場から拍手)