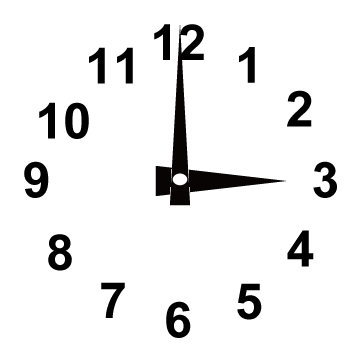前ページ/Page 1/次ページ

パネルディスカッション
「表現の自由と平和について」



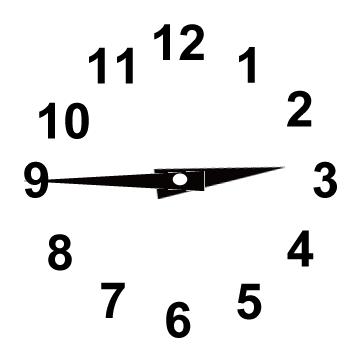 司会・川上美砂/第二部のはじめは、狛江に縁の深い3人の表現者に登場していただきます。その3人をご紹介しましょう。
司会・川上美砂/第二部のはじめは、狛江に縁の深い3人の表現者に登場していただきます。その3人をご紹介しましょう。川柳作家であり詩人の高鶴礼子さんは、全日本川柳協会常任幹事で、狛江で生まれた「川柳・狛の会」の指導もしていらっしゃいます。国際人権団体・アジア太平洋人権情報センターの機関誌に「表現すること」と題して原稿を寄せていらっしゃいます。
国際ジャーナリストの伊藤千尋さんは、元朝日新聞の記者です。中南米・ヨーロッパ・アメリカなどの特派員を歴任され、「コスタリカ平和の会」の共同代表でもあります。著書は多数ですが、音楽や 映画にも造詣が深く、その方面の新聞や雑誌にも連載していらっしゃいます。狛江在住です。
そして、先ほど素晴らしいクラリネットの演奏を聞かせてくださった木津陽介さん。この3人で「表現の自由と平和について」というテーマでお話しいただきます。
なお、コーディネータは、一番右側に座っていますが、こまえ平和フェスタで音楽と言えばこの方、大熊 啓さんです。黒いおヒゲと黒いシャツ・ズボン。先ほど、黒いスニーカーから黒い革靴に履き替えてきました。
では、この3人とコーディネータで、シンポジウムを行いたいと思います。どうぞ耳を傾けてお聴きください。
 大熊 啓/今回のコーディネータを務めます大熊です。先ほど司会からもご紹介いただきましたが、改めましてそれぞれのお口から、狛江との縁も含めて、ちょっと自己紹介していただければと思います。じゃあ、若手から、木津さんからお願いします。
大熊 啓/今回のコーディネータを務めます大熊です。先ほど司会からもご紹介いただきましたが、改めましてそれぞれのお口から、狛江との縁も含めて、ちょっと自己紹介していただければと思います。じゃあ、若手から、木津さんからお願いします。
ブラジルから帰ってくるときに、日本に家がなかったので、どこかないかと探したら、朝日新聞でアルバイトをしている女の子が、長州毛利家のお姫様だった。この人が東京に家が3軒ある。そのひとつが狛江にある。「じゃあ、1軒貸してね」と言って、そこに住んだんです。岩戸南でした。
住んだのはいいんだけど、お屋敷なのでお金がかかって仕方ない。これじゃもたない。でもいい街だなぁと思って、この狛江で生活し始めて、来年で30年です。(会場から拍手)
狛江市さんとのご縁は、今から6年ぐらい前になりますか、2010年に中央公民館さんが、川柳の何回かの講座をご企画くださいまして、お招きにあずかりました。以来、毎月1回、講座終了後にできた「川柳 狛の会」のみなさんとともに川柳を考え、いろんな出会いを愉しむということで、お伺いさせていただいている次第です。(会場から拍手)
小さいころから本を読んだり、ものを書いたりするのが好きな子どもではありました。大学を卒業しましたあと、私はテレビ番組制作のADをやっていまして、あと日本語教師などをやっていたのですが、ひとり目の子どもを妊娠したときに、流産しかかってしまったんです。入院と手術が続いて、仕事が続けられなくなってしまって。川柳と出会ったのは、そうやって仕事を辞めて、何年か経ったときのことでした。
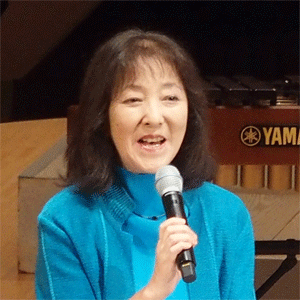 うちの近所に小さな古本屋さんがあって、ある日そこへ行ったんです。そこである本を手にとってぱらぱらっとめくったところに、それはありました。時実新子 (ときざね・しんこ) という人が書いた「五・七・五」、たった17音字のことばです。
うちの近所に小さな古本屋さんがあって、ある日そこへ行ったんです。そこである本を手にとってぱらぱらっとめくったところに、それはありました。時実新子 (ときざね・しんこ) という人が書いた「五・七・五」、たった17音字のことばです。
時実新子/1929年(昭和4年)~2007年(平成19年):彼女の川柳は、女性の情念を率直に、かつ、激しく表現したものが多い。その作風から川柳界の与謝野晶子と呼ばれた。(出典:Wikipedia)
当時の私は、川柳について何も知りませんでした。川柳といえば、ときどき新聞の片隅なんかに載っていて、なんか人をツンツクするみたいにして、時の為政者であるとか、世相を批判したり揶揄したり、それから「あはは」って笑えるけど、笑ってそれだけのような、とても人が一生賭けて向き合う対象であるなんて認識はなかったんです。
ましてや、時実新子なんていう名前も知りませんでした。ちなみに、初めて名前を聞かれる方もいらっしゃるかも知れませんから申し上げますと、新子は、「川柳界の与謝野晶子」と例えられるような存在です。
とにかく何も知らなかったですが、その句は、私に、こんなふうに語りかけてくれていました。「ご覧なさい。これが川柳というものなのですよ。」 そうか、これが川柳なのか。そうであるならば、「私は川柳がやりたい。」そんな強い思いが込み上げてまいりました。
本を買って、うちに帰って出版社に電話して、時実新子なる方の連絡先を訊きました。神戸にお住まいでした。それで、一生懸命手紙を書いたんです。もう自分でも笑えてくるほど、なんでこんなに一生懸命手紙を書いてるんだろうと思えるほど。思いのありったけを込めました。お返事は、ほどなくして届きました。
「見てさしあげます。毎月15句を私のところに書いていらしてください。」で、ヤッターと思って、鉛筆をぐっと握りしめた。それが始まりです。(会場から拍手)
「いちめんの椿の中に椿落つ」
 それから、高校になって生徒会長になったんです。これがまたおもしろい。高校のときには、弁論部というのをやりましてね。ここで、政治というもののおもしろさを知ったんです。
それから、高校になって生徒会長になったんです。これがまたおもしろい。高校のときには、弁論部というのをやりましてね。ここで、政治というもののおもしろさを知ったんです。僕は、出身が山口県なもんですから、しかも高校を卒業するときには、ちょうど明治維新100年ですよ。で、山口県から東京を目指そうというような男は、やっぱり総理大臣を目指すんですね。(会場から笑い) 本当に総理大臣になろうと思ってました。
ところが、大学に入って2か月目に、機動隊が大学に入りまして、僕たちは大学闘争というのが始まって、大学の先生がおろおろしたのを見て、ここで権威というものが、崩壊しちゃったんです。 同時に、日本の政治って、年功序列じゃないですか。たらい回しがどうのとか。こいつら本当に、ちゃんとした頭を持ってるのかという疑問も出てきて、本当の政治家じゃない(と思った)。当時、ベトナム反戦闘争とかあったじゃないですか。(木津さんに向かって)あったって知らない?
大学2年のときにキューバに行ったんです。別に、キューバの社会主義がどうのこうのというのではなく、違う社会を見ようと思ったんですよ。
そこで半年間キューバに行って、キューバ人と一緒にサトウキビを買って。帰ってきて、キューバというのがこういうところだというのを大学新聞に連載したんです。これが元で、知らせるということの醍醐味というのを知った。そこがきっかけです。
探検家になりたくて、政治家になりたくて、でも、ある意味、今、全部やってますよね。
 というのはですね、私は小さいころから歴史が大好きで、日本史・世界史、とくに日本の戦国時代が大好きなんですけども、そういった歴史を勉強するにつけ、テレビから流れてくる国会議員の歴史観のなさ、センスのない発言。そういったものに対して、憤りを覚えておりまして、間違った感覚を、僕が議員になって正してやろうと。非常に志が高くて、進学校の高校に進学しました。
というのはですね、私は小さいころから歴史が大好きで、日本史・世界史、とくに日本の戦国時代が大好きなんですけども、そういった歴史を勉強するにつけ、テレビから流れてくる国会議員の歴史観のなさ、センスのない発言。そういったものに対して、憤りを覚えておりまして、間違った感覚を、僕が議員になって正してやろうと。非常に志が高くて、進学校の高校に進学しました。ずっと勉強しながら、歴史が好きで、もちろん音楽も同じぐらい好きなんですけども、大学は京都大学の史学科に行きたいと思っていて勉強していました。ちょうど奈良に親戚もいましたので、奈良と京都で通えばなかなかいいんじゃないかと思って、勉強していたのですが、高校生に入りますと文系か理系かと進路をざっくり決めなくてはいけない。その進路をざっくり決めるときに、私が音楽家・クラリネット奏者として初めて出会ったプレーヤー(演奏家)なんですけども、ちょうど日本にベルリンフィルが演奏に来まして、今はもう退団されていますが、首席クラリネット奏者の、カール・ライスターさん というドイツの有名なプレーヤーがおりまして、その方が、モーツァルトのクラリネット協奏曲を演奏して、その場にちょうどチケットを買って客席で聴く機会があったんです。
Karl Leister (1937~): ドイツのクラリネット奏者。世界を代表するクラリネット奏者の一人。22歳でベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の首席奏者に就任、1993年まで務めた。(出典;Wikipedia)