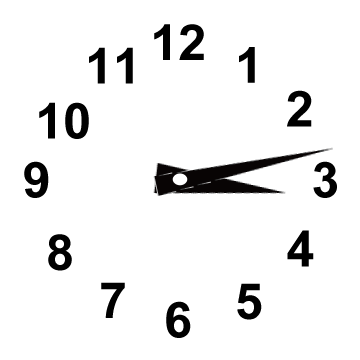パネルディスカッション
「表現の自由と平和について」



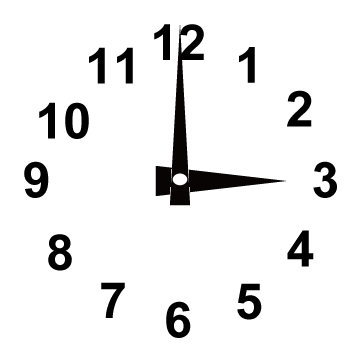 大熊/いやぁ、もしねぇ、伊藤さんが総理大臣になっていて、木津さんが国会議員になっていたら、今この国はどうなっているんだろうと思いますけど。(笑)
大熊/いやぁ、もしねぇ、伊藤さんが総理大臣になっていて、木津さんが国会議員になっていたら、今この国はどうなっているんだろうと思いますけど。(笑)さて、今回のテーマ「表現の自由と平和」ということでございますが、最近、表現の自由ということについては、フジロックフェスティバル が、ことし行われる中で、SEALDs (シールズ) という学生さんが、参加するということで、音楽に政治を持ち込むんじゃないという話もあったりして、私自身も、「そうかな?」って思っていたんですが、それぞれの思いを、今感じていらっしゃる表現の自由と政治に関して、また(表現の自由と)戦争について、それぞれの関わる分野から、木津さんなら音楽という分野、また、伊藤さんでしたら、あちこち世界を回って来ての話。また、高鶴さんは、ぜひ文学というものが戦時中にどういう役割を果たしてしまったのかとか、あるいは、それに抵抗してきたのか、それぞれ少しお話を聞かせていただければと思うんですが。
フジロックフェスティバル (FUJI ROCK FESTIVAL): 1997年、山梨県富士天神山スキー場で初開催された。1999年より、毎年7月下旬または8月上旬、新潟県湯沢町の苗場スキー場で開催されている。(出典:Wikipedia)
SEALDs (シールズ): 英語 Students Emergency Action for Liberal Democracy (自由と民主主義のための学生緊急行動) の略。2015年5月から2016年8月まで活動していた日本の学生団体。(出典:Wikipedia)
きょう、こういうパネルディスカッションの中で、あまたいる作曲家の中で、具体的にどこを取り上げてみなさまにお話ししたら、そうした思いが伝わるのかと思って、私のほうで4名挙げさせていただきました。
まずは、誰もが知っている、あの音楽室にある怖そうな風貌を持つ、ベートーベン。それから、ピアノを弾いている方なら非常に親近感があるのではないかと思いますが、ショパン。それから、近現代のロシアと切っても切り離せない、ショスタコーヴィチ。それから最後は、第二次世界大戦ヒットラーと切っても切り離せない、ワーグナー。この4人を、少し歴史を追って行く中で、お話をしていけたらと思っております。
で、クラシック音楽に限定してお話させていただきますが、さまざまな分野があります。例えば、大人数のオーケストラで演奏する交響曲。それから、弦楽器4人、バイオリン2本、ビオラ、チェロという比較的小さな人数で演奏される弦楽四重奏曲。それから、ピアノ1台で奏でられるピアノソナタあるいはエチュードと呼ばれるもの。大体、作曲家はこの3つの編成を使い分けて、いつの時代も書いています。
この3つというのが非常に大事になってくるのですが、交響曲というのは、こういう大きなホールで演奏する機会が多い作品ですので、基本的には自己・自分の芸術性をお客さまに披露するために演奏するのが、交響曲と呼ばれる大きな編成のオーケストラの曲です。
対照的なのは、弦楽四重奏と呼ばれる小さな編成で演奏する場合は、自分の置かれた人間関係や立場が不安定なとき、微妙なときに、比較的そういう見る目が少ない私的な演奏会でやられる弦楽四重奏というスタイルを採っています。 さらに、ピアノソナタというピアノ1台で演奏する曲というのは、もう自分自身の内面や心情をありのままに掻き出すために書いているというのが、ジャンルとしては挙げられます。
少し時代を遡ってお話してみようと思います。ここは、ぐじゃぐじゃになってしまうと取り返しがつかなくなりますので、頭の中を、みなさんフランス革命にしていただきたいと思います。これからお話しますのは、フランス革命のころのベートーベンとナポレオンのお話です。ベートーベンの交響曲の中に第3番「英雄」/「エロイカ」と呼ばれる交響曲があります。もともとは、「ナポレオンに捧ぐ」という副題が付いておりました。もちろん、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、平民出身のベートーベンは、同じく平民出身のナポレオンを熱烈に支持していました。ところが、熱烈に支持していたにもかかわらず、(ナポレオンが)皇帝に即位します。クーデターで即位するわけですけども、その瞬間に「なんだあいつも権力になびきやがった。ちくしょう、ふざけるな。」ということで、その「ナポレオンに捧ぐ」という副題をペンで、穴があくぐらい書きなぐって破り捨てて、「ある英雄だった男に捧ぐ」というタイトルに書き換えてしまった。
かえって、献呈するにあたって、そういった不吉なものを献呈するのはいかがなものかという判断があったと一部では言われています。
ちょっと簡単なんですが、歌詞の一節を紹介したいと思います。日本語訳の部分で一番有名なところだけ、ちょっと読みます。
すべての者は自然の胸に抱かれ、その乳房から歓びをいっぱいに飲んでいる。
邪(よこしま)な者、みなすべてバラの香りに誘われて自然の懐に入って行く。
自然は私たちに口づけとぶどう、死の試練をくぐり抜けた友を与えてくれた。
快楽などは、ウジ虫に投げ与えてしまう。
地と生を司る天使が、神の前に姿を現す。
こういった内容が、永遠高らかと歌われています。この第九をめぐるエピソードというのは、実はちょっとあとでお話しますショスタコーヴィチにも、少し関係してくるところでもありますので、何となく頭の片隅に置いておいていただければと思います。
邪(よこしま)な者、みなすべてバラの香りに誘われて自然の懐に入って行く。
自然は私たちに口づけとぶどう、死の試練をくぐり抜けた友を与えてくれた。
快楽などは、ウジ虫に投げ与えてしまう。
地と生を司る天使が、神の前に姿を現す。
そんな時代に、何度も何度もコールが続いたので、それまで客席でじっと身を潜めていた秘密警察が、数を数えたんでしょうね、きっと。有能なのか、お時間があるのか分からないですけど、「あ、5回目だ」と言って、一斉に逮捕に動いたというエピソードが残っています。これが初演のころ。